

TRUMEやオリエントといったブランドを擁するセイコーエプソンのウエアラブル機器事業部WP戦略企画部長の吉田和司氏。同部を牽引するいわば司令塔。他社に所属していた吉田氏は、オリエントの魅力に引かれてセイコーエプソンに入社。以降、プロダクトから販売戦略に至るオリエントの在り方を一新した。2019年7月、営業本部副本部長兼ウエアラブル機器事業部WP戦略企画部長に就任。
1950年に誕生したオリエントは、90年代以降、困難な時期を迎えることとなる。
2003年に上場廃止となったオリエント時計を救ったのは、セイコーエプソンだった。
同社は、09年にオリエント時計を完全子会社化。17年には、一層のシナジーを生むべく、エプソンに統合した。以降の大きな変化をもたらしたのは、旧オリエント時計生え抜きの人々と、そしてエプソンから新しく加わった人々である。
彼らに、オリエントの“今”とその未来を語ってもらうことにしよう。
「正直、一時期のオリエントは進むべき方向性に迷いがあったと思います」。こう語るのは、セイコーエプソンで営業本部の副本部長を務める吉田和司氏だ。かつて海外事業推進やマーケティングを行っていた彼は、「オリエントはなぜもっと自分の強みを活かした展開をしないのだろう?」と当時、オリエントを外から見ていたという。セイコーエプソンから声が掛かったのはちょうどその頃である。彼に迷いはなかった。
「2018年入社後は、「オリエントがこんなことを仕掛けてきたら脅威だな」と思っていたことを意識的に実行していった。「特徴的なデザインと奇抜なカラーリング、そして面白いテーマを追求することがオリエントらしさであり、強みだと感じましたね」。
吉田氏とオリエントの開発陣は何度も議論を重ね、2018年にはオリエントとオリエントスターの新たな方向性が定まった。オリエントは過去の遺産を今にリバイバルさせ、オリエントスターは機械式時計の未来を見せていく。吉田氏は進行中の企画をすべて見直しさせて、オリエントらしいプロダクトにフォーカスした。加えて、製品の質を大きく高めたのである。
「かつて諏訪精工舎(現セイコーエプソン)は非常に精度の高い機械式ムーブメントを作っていました。その技術を使って、まずはベースムーブメントの46系を改良しようとなった。その上で、スケルトンやムーンフェイズといったプラスアルファを重ねていけばいい」(吉田氏)。
1971年に発表された46系ムーブメントは、優れた巻き上げ効率と頑強な設計を持つ自動巻きムーブメントだったが、2017年の時点では、さすがに設計の古さは隠しようがなかった。改良を手掛けたのはウエアラブル機器事業部WP開発設計部の髙野正志氏だった。
「ムーブメントの基準は、オリエントよりもエプソンのほうが厳しいですね。例えば、歯車とムーブメントの隙間。旧オリエントは比較的大きかったのですが、エプソンは小さい。部品のばらつきに対してもエプソンはより厳密です。46系の改良は設計だけでなく、製造工程の見直しから行いました」
時計の機能として信頼できること、そして精度は必須だと髙野氏は語る。その上で、スケルトンのような試みができるようになった。
「昔の46系と今の46系では、香箱、3番車、ガンギ車とアンクル、テンプが同じですが、それ以外は別物。4番車や地板などを薄くすることで、ムーブメントも薄くなりました。また、スケルトンモデルに向くように、地板に打ち込んだピンの位置なども変えています」(髙野氏)
以降、オリエントスターは、スケルトンモデルを充実させることができた。
吉田氏と共にオリエントの方向性を形作ってきたのが、WP戦略企画部の石黒聡氏だ。彼はこう語る。「オリエントのデザインにはチャレンジ精神がありますね。1965年に発表された『万年カレンダー』が好例でしょう。他がやらないデザインやカラーリングを商品に落とし込むのがオリエントの精神です」。
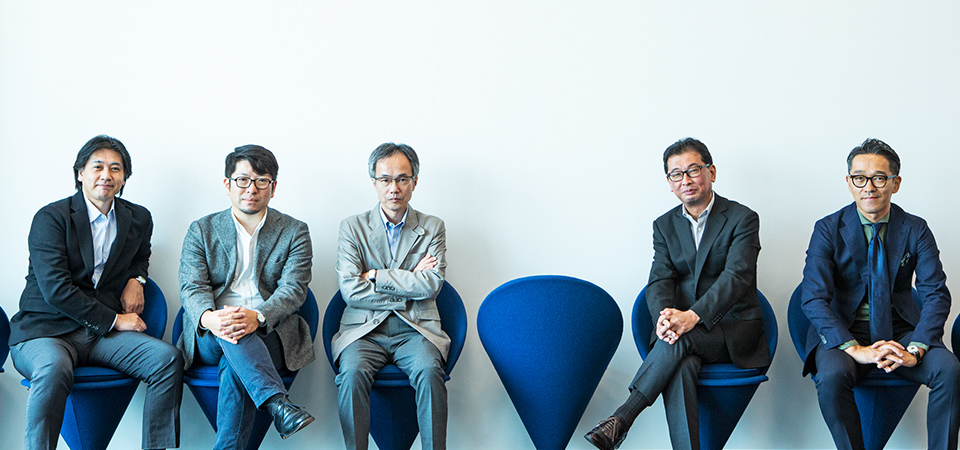
新生オリエントを支える人々。右から、WP企画設計部の田邉大輔氏。プロダクト全般の責任者だ。WP戦略企画部課長の石黒聡氏は、WP戦略企画部長の吉田和司氏と共にオリエントの方向性を定める人物。1971年に開発された46系ムーブメントを刷新したのは、WP開発設計部の髙野正志氏。彼はセイコーエプソンのより厳しい基準を持ち込み、46系ムーブメントの信頼性と精度をさらに高めた。オリエントのデザインを主導するのはデザイナーの冨下公平氏と久米克典氏だ。オリエントが誇る過去の資産を受け継ぎつつも、現代にフィットさせる重責を担う。
2018年、オリエントは1960年代から70年代のヘリテージを中心に見つめ直し、活かしていくこと基本に掲げた。それはオリエントのオリジナリティーに立ち返る作業だと石黒氏は語る。その第1弾として登場したのが「ウィークリーオートオリエントキングダイバー」だ。
デザインを手掛けた久米克典氏は語る。「オリジナルの造形と雰囲気を残したダイバーズウォッチを作ろうと思いました。針は新規設計で、ベルトも新しく起こしましたが、当時のデザインに戻ろうということで、曜日の表記などはオリジナルからトレースしました。ただ、多くの人に使ってもらいたいから価格は500ドル以下に抑えたかった」。風防をサファイアクリスタルではなく無機ガラスにしたのも価格を抑えるため。しかし価格を感じさせない丁寧な作り込みは、いかにも今のオリエントだ。
一方でオリエントは、より“らしい”モデルもリリースする。それが2005年に発表されたレトロフューチャーシリーズの復刻版だ。オリジナルモデルは遊び心に溢れていたが、デザイナーの冨下公平氏曰く、復刻版はさらに機械式レンジファインダーカメラのディテールを盛り込んだ、という。オリエントにしか採用できない、かなり野心的な意匠だ。
「社内でデザインコンペを行い、カメラが採用されました。これぞオリエントという企画ですよね。機械式時計に興味を持ってもらうため、セミスケルトンを採用しました。ただし視認性は損ねず、価格も控えめにしています。エントリーでも普段使いできる時計というオリエントのスタンスをキープすることが重要だと思っています」(冨下氏)。彼らが口を揃えて強調するのが、オリエントが持つ“資産”の豊かさだ。「ダイバーズウォッチの中にも、昔のカレンダーオートオリエントダイバーのような良い資産があります。使いたいモチーフは数え切れないほどありますが、今のニーズにあったものを採用していきたいですね」(冨下氏)。
そういった資産の中で、オリエントのデザイナーたちがとりわけ注目するのが、グラデーションの付いた「ジャガーフォーカス」だ。文字盤の外周に別の色をあしらい、色を強調する。今でこそポピュラーになったが、この手法の先駆者は、間違いなく1970年代のオリエントだ。
一時期、オリエントは数え切れないほどのフォーカス(グラデーション)文字盤をリリースした。結果、「昔のサンプルが山のようにある」(冨下氏)という。かつて謳っていたように「カラーのことなら、常に先を行く『オリエント・カラーウォッチ』」を目指すのだろう。石黒氏が補足する。「オリエントは定番も強いメーカーなのです。プレゼンスを高めるためにはフォーカス文字盤は有効でしょう」。ジャガーフォーカスに並ぶオリエントの代名詞、「万年カレンダー」の復刻予定はあるのか?「万年カレンダーは、いかにもオリエントらしい時計ですので大切な資産として考えています」。やらないとは言わないのが、今のオリエントの勢いを示している。



過去の資産を積極的に活用するようになったオリエント。今回の開発陣との合同インタビューに際し、懐かしのヒストリカルピースの数々が用意された。1960年代から70年代にかけてオリエントは、多彩なコレクションで他社との差別化を図った。中央の写真のモデルは、2020年に発表される復刻版。いずれもオリエントらしい要素に満ちている。
2018年以降、デザインとユニークな機能にフォーカスするオリエント。「中途半端なデザインはダメ」「あまり大きなマスは狙わない」というコメントからもそれはうかがえる。一方で、オリエントは手堅い実用時計を作るメーカーという側面を決して忘れてはいない。新生オリエントが46系ムーブメントの改良から始めたことが、それを証す。異端児と言われるオリエントが、海外で広く支持されてきた一因に、手堅い物作りがある。
WP企画設計部の田邉大輔氏は語る。「オリエントはグローバルブランドです。ですから、時計としてのスタンダードは押さえていなければならない。その上で、デザインを広げて人々に訴求していきたいのです」。こうした実用時計としての見直しは細部にまで及ぶ。例えば46系F7の長針。久米氏は言う。「オリエントスターの分針は、長さを16㎜まで増やしました。理由は、視認性を確保するため」。トルクを要するため、普通、時計メーカーは針を伸ばしたがらない。しかし、オリエントはあえて踏み切ったのである。
「私たちはロービートの機械式ムーブメントで一層精度を高めたいと思っています。セイコーエプソンにはスイスの天文台コンクールに出品し、上位を独占した歴史と技術の蓄積があります。そうした技術を投じたら、機械式時計は面白くなると思いませんか? そして、オリエントスターはメイド・イン・ジャパンであること、秋田製であることをもっと打ち出します」(吉田氏)
中途半端は面白くない、好きな時計作りをやりたい、と言い切るオリエントを創る人々。その疾走感は、彼らが見つめ直そうとしている1960年代から70年代のオリエントそのものではないだろうか。かつての迷いはすでになく、オリエントはついに復活を遂げたのである。
※クロノス日本版より転載